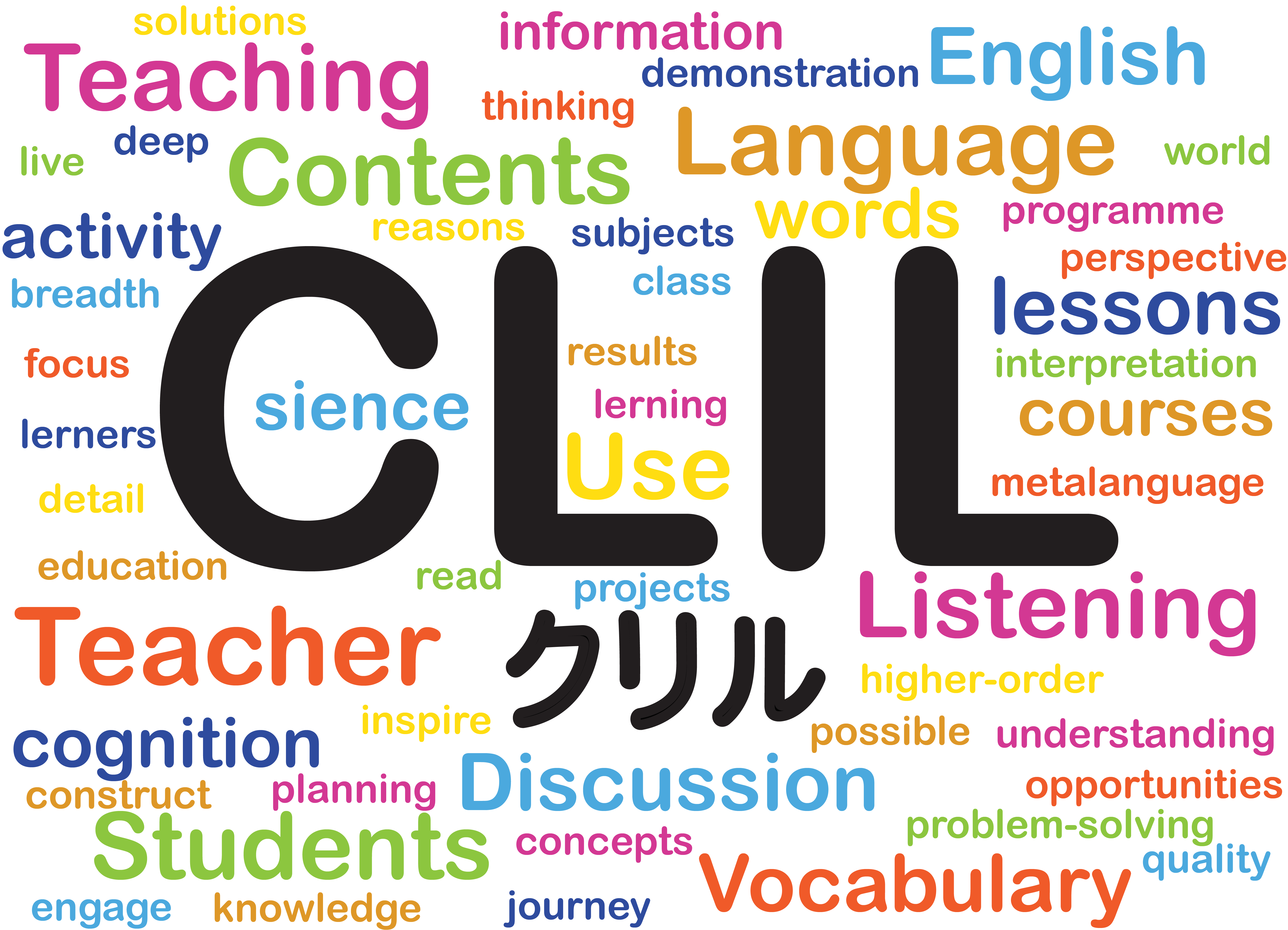クリルCLI LとはContent and Language Integrated Learningの略語で、教授法の一つです。
日本では内容言語統合型学習という言い方もあるようですが、クリルの方が簡単で覚えやすいので、一般的にはクリルで定着してきているように思います。
クリルは内容のある教科を教える際にターゲットの言語を通して科目の内容の学習の達成を目指すものです。言語と内容を同時に学べると言う側面を持った教授法です。
想像しやすいように例を挙げると、日本で日本語を母国語とする子どもがインターナショナルスクールに行った場合、子どもは算数、理科、社会、音楽、図画工作、体育などの内容のある科目を英語(ターゲット言語)で学ぶ事んでいますね。
日本のインターナショナルスクールがCLILを採用しているかどうかは分かりませんが、例として挙げました。
私は10年以上に渡り、クリル教授法で理科、社会、地理、算数、体育、図画工作、コンピューターなどの科目を日本語を母国語としない現地小学生に日本語で教えて来ました。直接法と似ていて、日本語を直接法で長年教えた経験があったので、教え方には苦労しませんでしたが、語彙をまだまだ知らない子どもにコンセプトを理解してもらうってのには大変苦労しています。

CLILで教科の内容を教える際には、Coyle’s CLIL’s 4Csとクリルのフレームワークとなるtriptychを理解する事がとっても大事です。別の機会に例を出しながら説明したいと思います。